中小企業こそ必要な経営計画の策定|作り方や作成するメリットを解説
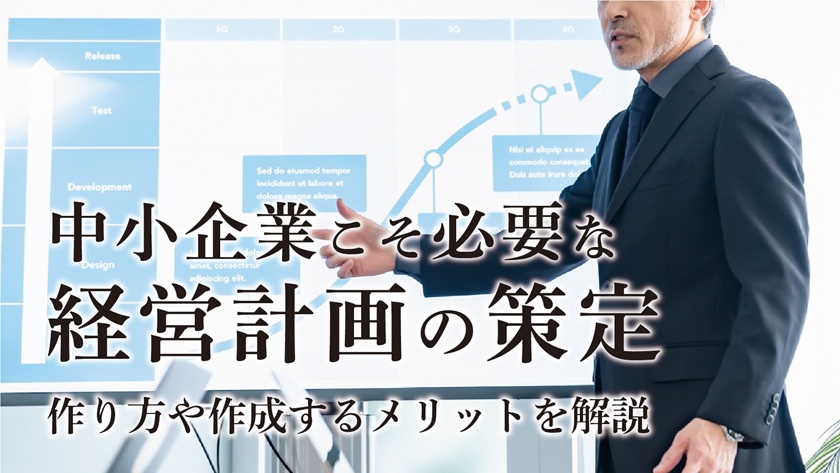
ビジネス環境が急速に変化し、競争が激化する中で、企業が持続的に成長するには、明確な方向性と戦略が必要です。しかし、近年はデジタル技術の発展により、企業間の差別化が難しくなり、似たような戦略を採用する企業が増えています。こうした状況の中で、自社の強みを活かし、競争の中で優位に立つには、事業の方向性を明確にし、計画的に成長を進める「経営計画」が求められます。特に中小企業は、大企業と比べて人材や資金などの経営資源が限られているため、無駄を省き、効率的に経営を進めるための指針として経営計画が欠かせません。
本記事では、経営計画の概要や作成するメリットを詳しく解説します。達成できる経営計画の作り方もあわせて紹介するので、ぜひ参考にしてください。
目次
・経営計画とは
・経営計画を作成する7つのメリット
・経営計画の種類
・経営計画の作り方
・達成できる経営計画策定のポイント
・まとめ
経営計画とは
経営計画とは、企業が目指す未来を実現するために、具体的な目標と行動指針を定めたものです。この計画を文書化したものを「経営計画書」と言います。
なお、経営計画は一度作成して終わりではありません。PDCAサイクル(計画・実行・評価・改善)を繰り返し回すことで、環境の変化に柔軟に対応し、会社の成長と存続を支える指針となります。経営者のビジョンや考えを明文化し、組織全体で共有することで、目標に向かって一丸となり、実現へと近づけるでしょう。
経営計画はなぜ必要なのか
経営計画は、企業の成長と安定経営のために欠かせない「設計図」です。計画がなければ、企業は進むべき方向を見失い、社員や顧客との間に認識のズレが生まれ、目標達成が難しくなります。建物を建てるときに設計図が必要なように、企業経営にも明確な計画が求められます。
また、たとえ社長が大きなビジョンや社会貢献への思いを持っていたとしても、それが社員に正しく伝わらなければ、組織全体の方向性は定まりません。経営計画は、社長のビジョンを具体的な行動計画に落とし込み、社員全員が共通の理解を持ち、同じ目標に向かって進むための土台となります。
さらに、経営計画は、社長の理想と市場や顧客ニーズとのズレを可視化し、ギャップを修正するための指針にもなります。経営計画を通じて、企業は環境の変化に柔軟に対応し、成長を維持するための基盤を築けるでしょう。
経営計画が必要な場面
経営計画は、以下のような場面で必要になります。
✓ 経営状況を改善したいとき
✓ 新規事業を始めるとき
✓ 資金調達したいとき
✓ 補助金を活用したいとき
✓ 社長が交代するとき など
必要な場面ごとにしっかり策定し、経営を安定させましょう。
事業計画書と経営計画の違い
先述したとおり、経営計画は、企業全体のビジョンや最終目標を明確にし、将来なりたい姿を描くためのグランドデザインです。会社全体の方向性や大きな目標を設定するもので、全社を視野に入れて策定されます。
一方、事業計画は、経営計画で設定された目標を実現するために、事業部門や部門ごとに具体的な行動計画を作成するものです。つまり、事業計画は経営計画を実行に移すための具体的なプランであり、経営計画の一部と言えます。
そのため、事業計画があれば経営計画は必要ないと考える経営者もいるかもしれません。しかし、実際には、経営計画がしっかりとした基盤を作らない限り、効果的な事業計画を立てることは難しくなります。両者は切り離して考えるべきではなく、経営計画が土台となり、その上で事業計画が具体的な行動に落とし込まれることを理解しておきましょう。
経営計画を作成する7つのメリット
経営計画を作成するメリットは、以下の7つです。
● 自社の現状を把握できる
● 企業成長を促進できる
● 進むべき道を明確にできる
● リスク管理ができる
● 従業員と目標を共有できる
● 信用力を高められる
● 事業継承がスムーズになる
企業経営では、事業の拡大や人材の確保、資金調達など、多くの重要な決断を経営者が下さなければなりません。その際、明確な方針がないと誤った判断をするリスクが高まります。しかし、経営計画をしっかり策定しておけば、企業が進むべき方向が明確になり、掲げたビジョンや目標に向かって組織を導けます。
また、企業の信用力は、外部の関係者からの評価によって決まります。経営計画があることで、社内だけでなく取引先や金融機関など外部からの信頼も高まり、資金調達や取引の継続にも有利に働きます。いざというときに備え、いつでも経営計画を提示できる状態を整えておくことが大切です。
経営計画の種類
経営計画の種類は、以下の3つです。
● 長期経営計画
● 中期経営計画
● 短期経営計画
3つの計画を段階的に積み重ねることで、企業は目標達成への道筋を明確に描き、着実に成長を遂げられます。安定した経営基盤を築くためにも、可能であれば全ての計画を整えることをおすすめします。
長期経営計画とは
長期経営計画は、5〜10年後の「ありたい姿」を明確にし、実現に向けた大きな方向性を示すものです。目先の利益にとらわれず、将来の市場変化や顧客ニーズを見据えながら、会社のビジョン、成長戦略、新規事業や投資方針などを定めます。今、何をどう進めるかを定めることで、将来に向けてしっかりとした道筋を描けるでしょう。
中期経営計画とは
中期経営計画は、長期経営計画で掲げた目標を達成するために、3〜5年の期間内で実行すべき戦略と具体的な方針を定めます。また、企業が直面している経営課題を明確にし、課題解決に向けた具体的な方法を示すことも大切です。
なお、中小企業の中には5〜10年先の予測は難しく、長期経営計画を作成しないケースもあります。その場合は、中期経営計画を策定し、将来のビジョンや目標を明確にしながら、達成すべき具体的な計画を立てるとよいでしょう。
短期経営計画とは
短期経営計画は、1年間の経営目標を達成するために必要な行動プランを定めます。企業によっては、「単年度計画」や「予算計画」とも呼ばれ、売上や経費、仕入れ、人件費などの数値目標を設定し、達成するための具体的な施策を明確にします。市場の変化や競合の動向に合わせて柔軟に対応しながら、経営目標を確実に実現するための道筋を描くことが重要です。
経営計画の作り方
効果的な経営計画を作成するための5つのステップを紹介します。
● 経営理念と目的の明確化
● 現状分析
● 外部環境分析
● 目標設定
● 進捗管理
それぞれを詳しく見ていきましょう。
経営理念と目的の明確化
最初に、企業の存在意義や経営の方向性を明確にすることが重要です。なぜ経営計画を立てるのか、その目的を明確にさせることで、計画に対する理解と実行力が高まります。例えば、「持続的な企業成長を実現する」「新規事業を展開し市場を拡大する」「経営方針を明文化し、社内外の関係者と共有する」などが目的として考えられます。
なお、企業の経営方針としては、自社の存在意義を示すミッションだけでなく、ビジョン(目指す未来の姿)やバリュー(企業の価値観)もあわせて明確にするケースが一般的です。3要素を定めることで、自社が目指す方向性が明確になり、経営理念に基づいた計画を立てやすくなります。
内部環境分析
内部環境分析では、「ヒト・モノ・カネ・情報」といった企業を支える要素を詳細に調査し、強みや課題を洗い出します。主な分析対象として、以下の項目が挙げられます。
✓ 人材の状況
✓ 顧客基盤
✓ 拠点の分布
✓ 設備・オフィス環境
✓ 社内システム・インフラ
✓ 企業文化・風土
✓ 顧客満足度
✓ 経営体制 など
また、数値化しにくい社内の雰囲気や企業文化、社員のモチベーションなども、従業員アンケートやヒアリングを通じて把握することが重要です。自社のリソースを客観的に分析することで、競争力のある分野や改善すべき点を明確にし、今後の経営戦略につなげられます。
外部環境分析
社内の状況を把握する内部環境分析を行った後は、以下のような外部環境を把握しましょう。
✓ 市場動向
✓ 競合企業の戦略
✓ 取引先の変化
✓ 消費者ニーズの変化
✓ 技術革新
✓ 法律や制度の改正
✓ 経済状況の変化
✓ 地域の人口動向 など
外部環境は企業の意向だけではコントロールできないため、予測が難しい側面もあります。しかし、適切な経営計画を策定するためには、最新の情報を常に収集し、変化に柔軟に対応できる体制を整えることが求められます。
目標設定
現状分析を踏まえ、企業が達成すべき目標を設定します。ここでは、売上や利益、市場シェアなど、具体的な数値目標を定めることが重要です。その上で、目標を達成するための具体的なアクションプランを策定します。
例えば、「3年後に売上10億円を達成する」「新たな販売チャネルを開拓し、顧客数を30%増加させる」など、達成すべき具体的な指標を設定します。さらに、目標を実現するために取り組むべき課題や、実行すべき業務・行動を明確に整理しましょう。
数値を用いた目標を定め、実現するための施策や戦略を具体化することで、実行可能な経営計画を立案できます。
経営計画の実行と継続的な見直し
経営計画は策定した時点で終わりではなく、実行に移してからが本当のスタートです。計画を形だけで終わらせず、実際の業務に落とし込み、定期的に進捗を確認しながら実行していくことが重要です。
また、経営環境は常に変化しています。そのため、計画を固定的なものとして扱うのではなく、必要に応じて適宜見直しを行うことが大切です。理想的には、3か月に1回、遅くとも1年に1回、計画の進捗や成果を検証し、現実に即した形に調整しましょう。
達成できる経営計画策定のポイント
経営計画を策定する際は、単に目標を掲げるだけでなく、実行可能で効果的な内容にすることが重要です。計画の精度を高め、実際の経営に活かすために、以下のポイントを押さえると良いでしょう。
● テンプレートを活用し、効率的に策定する
● 量より質を重視し、実現可能な計画を立てる
● 税理士に依頼し、精度を高める
経営計画をゼロから作るのは時間も手間もかかります。テンプレートを活用するなど、基本的な枠組みを活用しつつ、自社に合わせた内容を盛り込みましょう。また、分厚い計画書を作っても、現実的でなければ意味がありません。質の高い経営計画を策定することで、会社の方向性が明確になり、実際の成果につなげられます。
経営計画策定を税理士に依頼する5つのメリット
税理士に経営計画策定を依頼することで得られるメリットは、以下の5つです。
✓ 専門知識を活用できる
✓ 税務視点から最適化してくれる
✓ リスク管理が向上する
✓ コア業務に集中できる
✓ 迅速かつスムーズに進められる
経営計画を立てる際、売上目標を決めただけでは、会社に残る利益を正確に算出できません。税理士に依頼することで、税負担を考慮した、現実的で再現性の高い経営計画を作成できます。顧問契約を結んでいる税理士であれば、会社の経営状況や財務状況を把握しているため、計画策定もスムーズに進むでしょう。
名古屋総合税理士法人では、経営計画の策定はもちろん、資金調達や節税対策、事業承継など経営に関わる税務をトータルサポートしております。「経営計画を作成したいが、どこから始めれば良いか分からない」「財務・税務の視点を加えた現実的な経営計画を作成したい」と悩んでいる方は、お気軽にご相談ください。
まとめ
経営計画の策定は、会社の利益向上や信頼獲得、成長のための土台作りです。特に中小企業は、市場環境や法規制の変化に敏感です。そのため、経営計画を全社員で共有し、日々の業務に反映させる企業とそうでない企業では、経営状況や成長スピードに大きな差が生まれます。経営計画をしっかりと策定し、実行することが、会社の成長を支えるポイントとなります。また、経営計画はリスク管理の観点からも重要です。突発的なトラブルや経済状況の変化にも柔軟に対応できるため、経営の安定性を高める効果が期待できるでしょう。